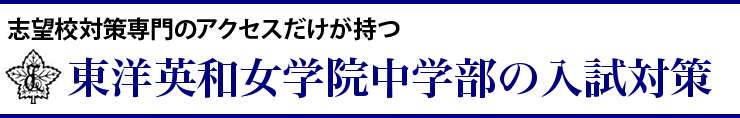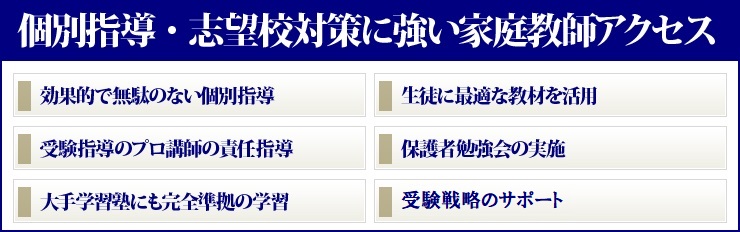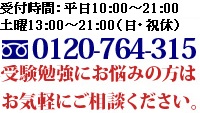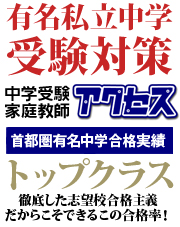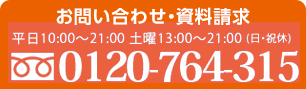総合難易度:★★★☆☆
算数難易度:★★★☆☆
国語難易度:★★★☆☆
理科難易度:★★★☆☆
社会難易度:★★★☆☆
算数難易度:★★★☆☆
国語難易度:★★★☆☆
理科難易度:★★★☆☆
社会難易度:★★★☆☆
東洋英和女学院中は、東京都港区にある完全中高一貫制の私立女子校です。
「敬神奉仕」の標語を基にしたキリスト教教育を行っており、毎朝の礼拝と、週1回の聖書の授業があります。
大学合格実績の面では、東洋英和女学院大学への院内推薦制度があるものの進学者はそれほど多くなく、他大学への合格実績は国公立大学、早慶上智等難関大学への進学を希望する生徒が多いのが特徴です。

①4科目とも基本~標準レベルの問題が多く解きやすいが、その分平均点が高い
②算数では解答用紙がなく、問題用紙に解答を記入する
③理社では単純な知識だけでなく、その背景・理由・結果などを問う問題が多い。

| 科目 | 配点 | 時間 | 問題数 | 難易度 | 記述・要途中式 | 要思考力問題率 | 難問出題率 | 出題タイプ | 合格最低ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 45分 | 普通 | 普通 | 20% | 15% | 5% | A | 64% |
| 算数 | 100点 | 45分 | やや多い | 普通 | 80% | 20% | 15% | AB | 64% |
| 理科 | 60点 | 30分 | やや多い | 普通 | 12% | 20% | 5% | A | 64% |
| 社会 | 60点 | 30分 | 普通 | 普通 | 15% | 10% | 10% | A | 64% |
| A タイプ |
全体の9割以上が知識や公式を知っていて、その活用法が分かっていれば解ける出題の学校。 | B タイプ |
全体の3割以上が正解を出すために、思考力や発想力を必要とする問題の学校。 | AB タイプ |
全体の1割から3割がBタイプ(正解を出すために思考力や発想力を必要とする問題)の学校。 |
|---|

| 科目 | 出題されやすい単元・形式 |
|---|---|
| 国語 | ●漢字の読み書き ●小説・物語文 ●随筆文 |
| 算数 | ●計算問題 ●特殊算 ●数の性質 ●速さ(旅人算、ヒストグラム) ●平面図形(求積) ●立体図形(体積、水そう、グラフ) |
| 理科 | ●物理・化学・生物・地学分野から幅広く出題 |
| 社会 | ●日本の地理 ●日本の歴史 ●公民 ●時事問題 |

| 科目 | 学習すべき内容・学習方法 | 試験での得点方法 |
|---|---|---|
| 国語 | 大問2題(設問数は約20問)の構成で、2題とも読解問題が出題される。漢字の読み書きは読解問題の中に内包される形で出題される。 出題内容としては、小説・物語文と随筆文から1題ずつ出題されることが多く、論説・説明文からの出題が少ないという特徴がある。小説・物語文と随筆文の読解演習を重点的に行うことが合格には必要不可欠になるだろう。その際、分からない言葉が出てきたら逐一国語辞典で調べるなどして語彙力をアップさせたい。 また、解答形式としては記号選択、抜き出し、記述(字数の多いものはあまり出題されない)が大半で、大問1では抜き出し・記述が中心、大問2では漢字・記号選択・抜き出しが中心となっている。 漢字は約10点分あり、ここでの失点はできるだけ避けたい。毎日漢字の練習をするなどして、漢字力を強化しよう。 | 大問1のボリュームがやや多いので、時間配分は大問1を少し多めに取る。 その上で、まずは大問1から解いていく。その際、記述問題は必ず記入し、空欄を作らないようにすること。 大問1が終わったら、大問2に取りかかる。 |
| 算数 | 大問10題(小問数は25問)の構成で、配点には偏りがなく1問4点となっている。 解答形式が特殊で、解答用紙がなく問題用紙に解答を書き込む形式となっているので注意が必要だ。 出題の傾向としては、大問1では計算問題、大問2では小問集合、大問3では図形問題、大問4・5では特殊算、大問6では数の性質、大問7では立体図形が出題され、これら大問1~7は基本~標準レベルのものが多い。大問8~10では難度の高い応用問題が出題され、図形(点の移動など)、数の性質、速さ(ヒストグラムなど)、比と割合などから出題される。 以上から分かるように、基本~標準レベルの大問1~7でいかにミスなく確実に得点し、応用レベルの大問8~10でいかに得点を稼げるかがポイントになる。出題分野の傾向がある程度はっきりしているので、頻出分野の演習を重点的に行うこと、なおかつミスを極力減らせるようにミスノートを作るなどして自分のミスしやすいポイントを把握することの2点が合格のためには必要になるだろう。 | まずは大問1~7の基本~標準レベルの問題を素早く正確に解く。その際、時間の浪費を抑えるために分からない問題は一旦飛ばして、どんどん先に進むことが重要だ。 大問1~7が終わったら、大問8~10に進む。比較的難易度の低い(1)は確実に解答したい。 また、45分間で大問10題と若干問題量が多く感じると思うので、時間配分には十分気を付けること。 |
| 理科 | 大問4題(小問数は約30問)の構成で、物理・化学・生物・地学分野からバランスよく出題されている。解答形式は記号選択・記述、計算、作図と幅広い形式で問われる。 難度は決して高くなく基本レベルのものが中心だが、単純に知識のみを問うのではなく、「知識の背景・理由」、「比較実験からどう結論を導くのかという科学実験の本質」など知識を少し深めて学習することがポイントになってくる。日ごろの学習の際から、理科を「暗記科目」として捉えるのではなく、「科学的思考力を養う科目」として捉えて学習することが合格に直結してくるだろう。「なぜそうなるのか?」と少しだけ踏み込んで考える習慣をつけたい。 | 基本問題が中心で難度の高い問題はそれほど多くないので、出来そうな問題から順次解いていく。 分からない問題は一旦飛ばすなどして、時間を浪費してしまうことだけは注意して解答を進めること。 |
| 社会 | 大問3題(小問数約30問)という問題構成で、地理、歴史、公民分野からバランスよく出題されている。また、公民では世界地理や世界情勢も含めて出題されることが少なくない。 解答形式としては、記号選択、適語記入、記述が中心。記述問題の比率が比較的多いのが東洋英和の特徴と言えるだろう。そのため記述問題対策がポイントとなるが、東洋英和の記述問題は、ある社会的事項に対する「原因(なぜそうなのか?)」、「結果(その結果、どうなるのか?)」と、「資料から読み取れる情報」を記述する問題の3つに大別される。そのため、日ごろの学習の際に知識を覚えるだけで終わらせずに、上記3点まで掘り下げて学ぶ習慣をつけることが重要になる。 記述以外では基本的な内容のものが大半を占めているので、社会の問題集を1冊しっかりと終わらせて、知識の抜けもれがない状態で試験に挑みたい。 | まずは記号選択・適語記入といった基本レベルの問題を素早く解答する。その際、できるだけ記述問題の時間を確保できるようにするのがポイントだ。 その後、腰を据えて記述問題に取り組む。空欄を絶対に作らないように心掛けよう。 |

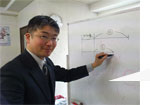
東洋英和女学院中合格に必要なのは、「基本~標準レベルの完成度」、「表面的ではなく一歩踏み込んだ理解」の2つです。
まず、4科目を通して基本~標準レベルでの出題が大半を占めているため、合格者平均点も高くなっています。そのため、基本~レベルの知識を正確かつ網羅的に学んでいることが合格に必要不可欠な条件と言えるでしょう。
また、特に理科・社会に言えることですが、表面的な知識だけだとある一定の得点までしか期待できず、その知識の「背景・原因・結果」まで理解していることが得点を上乗せするうえで必要不可欠になります。「知識科目」と呼ばれる理科・社会ですが、「表面的な知識」に終始することなく「本質的な知識」にまで掘り下げて学習することが東洋英和では求められています。