
| 学校名 | 明大明治中学校 |
|---|---|
| 共学・別学 | 共学校 |
| 住所 | 〒182-0033 東京都調布市富士見町4丁目23−25 |
| ホームページ |
総合難易度:★★★★☆
- 算数難易度:★★★★☆
- 国語難易度:★★★★☆
- 理科難易度:★★★★☆
- 社会難易度:★★★★☆
明大明治中学校について
明大明治中は、東京都調布市にある男女共学の中高一貫校です。
大学受験で最も志願者の多い明治大学の直系付属校であるため人気は高く、私大付属校としては早慶の付属校と並んで最難関に位置付けられています。
近年は他大学への進学も少し増え、約85%の卒業生が明治大学に進学しています。
私立大学の併願も一部可能になったところもあり、私立の他大学への進学も増加しています。
入試の特長
①基礎知識に加え、思考力・表現力を見る問題が数多く出題されます。
②国語は説明文を中心に長文1題と漢字1題が出題されています。
③算数は計算・一行題以外は途中式が求められています。
科目別の分析
科目別出題形式・タイプ分析
| 科目 | 配点 | 時間 | 問題数 | 難易度 | 記述・要途中式 | 要記述問題率 | 難問出題率 | 出題タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 50分 | やや多 | やや難 | 40% | 30% | 15% | AB |
| 算数 | 100点 | 50分 | 標準 | やや難 | 80% | 40% | 20% | B |
| 理科 | 75点 | 40分 | やや多 | やや難 | 5% | 20% | 10% | AB |
| 社会 | 75点 | 40分 | やや多 | やや難 | 30% | 20% | 10% | AB |
出題タイプの解説
- Aタイプ全体の9割以上が知識や公式を知っていて、その活用法が分かっていれば解ける出題の学校。
- Bタイプ全体の3割以上が正解を出すために、思考力や発想力を必要とする問題の学校。
- ABタイプ全体の1割から3割がBタイプ(正解を出すために思考力や発想力を必要とする問題)の学校。
科目別出題傾向
| 科目 | 出題されやすい単元・形式 |
|---|---|
| 国語 |
●論説文・説明文 ●言葉の知識 ● 漢字の書き取り |
| 算数 |
●特殊算(差集め算、還元算、過不足算) ●場合の数 ●速さ(旅人算) ●ニュートン算 ●図形(相似、移動、求積) |
| 理科 |
●物理(電気、計算) ●化学(気体、水溶液、計算) ●生物(植物、動物、からだのしくみ) ●地学(地層、火山、岩石、天体) |
| 社会 |
●地理総合問題 ●歴史総合問題 ●政治総合問題 ●時事問題 |
明大明治中学校の科目別攻略方法
国語の攻略方法
国語の出題傾向と学習方法
説明文を中心にした長文問題が出題されます。限られた時間内で、論理的な長い文章を素早く読み解く力が必要です。そのために言葉の知識をつけていくことも大事です。
要旨や主題を聞かれる100字程度の記述があります。長文からキーワードに注意して、筆者の主張を読み取り、それを的確にまとめる訓練が必須です。
記述で点数をもらえるポイントを書けるように、長文を素早く正確に読めるように、アクセスの講師と一緒に、過去問を使いながら学習していきましょう。
漢字もトメ・ハネ・ハライにも気を付け、丁寧に書く習慣をつけましょう。
試験で高得点をとるポイント
まずは、漢字の書き取りを手早く解きましょう。減点されないように、画数・バランスに気を付けて丁寧に書きましょう。
50分の時間内で、漢字を解いた後、かなりの長文を読み解かないといけないので、設問を解きつつ文章を読んでいく方が良いかもしれません。読み解きながら、文章を捉えて、最後の記述問題をまとめられるようにしてください。
算数の攻略方法
算数の出題傾向と学習方法
大問5題の構成です。問1は計算と一行題で答えのみです。ここでケアレスミスせずにしっかりと解きましょう。
計算を毎日欠かさず練習して計算力を養ってください。問2以降は、途中式、考え方を書く応用問題です。途中式や考え方が正しければ、解答が不正解でも部分点がもらえますので、普段から途中式を書く習慣を付けてください。
思考力を見る問題が出題されますので、与えられた条件を整理して、論理的に考えていけるように、過去問と合わせて同レベルの学校の入試問題も取り組んで力を付けてください。
試験で高得点をとるポイント
計算、一行題は素早く正確に解いてください。ケアレスミスにも気をつけて、見直しの時間も取り、取りこぼしの内容にしてください。
問2以降の応用問題、時間がかかりそうな問題は、ある程度見極めていくことも必要です。
途中式や考え方は、採点者に伝わるように、見やすく書きましょう。
理科の攻略方法
理科の出題傾向と学習方法
大問数は7題で、物理・化学・生物・地学から1題ずつ、分野もバランスよく出題されます。実験結果や観察から分かることを見つける科学的考察力、計算力が求められています。
日ごろから分析・考察問題に取り組むと同時に生活の周りにある科学に対して興味を持ち、自分なりに考えるという姿勢が重要になってきます。小学校の実験でも積極的に学びましょう。基本となる「知識」を身に付け、計算問題は充分な演習を繰り返して高いレベルで習得しておきましょう。
時事がらみの問題が出題されることもありますので、普段から環境問題や科学に関するニュース等にも気を付けてください。
試験で高得点をとるポイント
40分で小問35~40問ぐらいを解かなければいけないので、スピードを意識してください。
分からない問題は一旦飛ばして後回しにしましょう。
知識関係、計算問題を素早く解き、実験観察等の分析・考察問題に時間を充てられるようにしましょう。
社会の攻略方法
社会の出題傾向と学習方法
大問数は3題で(小問数は40問前後)、地理・歴史・公民からバランスよく出題されています。分野をまたがって出される問題が出題されることもあります。
地形図、地図、表、グラフ等の資料が多用されています。資料やリード文などから読み取れる内容を手がかりにして考え、問われていることに正しく解答していかないとなりません。自分の考えも反映させて答える問題も出題されます。
基礎知識を早く身に付けて、考察問題を解けるように、他校の過去問も使いながら学習していきましょう。漢字指定があるので、正しく書けるように日々学習してください。
試験で高得点をとるポイント
問題数も多く、読む文章・資料も多いので、時間配分にも十分気を付けましょう。
文章や資料から読み取れること、分かることを書きこんでいき、条件を整理して、論理的に考えられるように進めていきましょう。
対策まとめ
お子さま一人ひとりに合った対策を、今から始めましょう
100人いれば100通りの受験。中学受験の対策は、お子さま一人ひとりで大きく変わります。
まずは現在の学習状況や目標を把握し、限られた時間の中でベストな方法をご提案いたします。
まずは無料相談で、お悩みをお聞かせください。今後の方向性を一緒に見つけましょう。
無料相談もこちらお問い合わせください

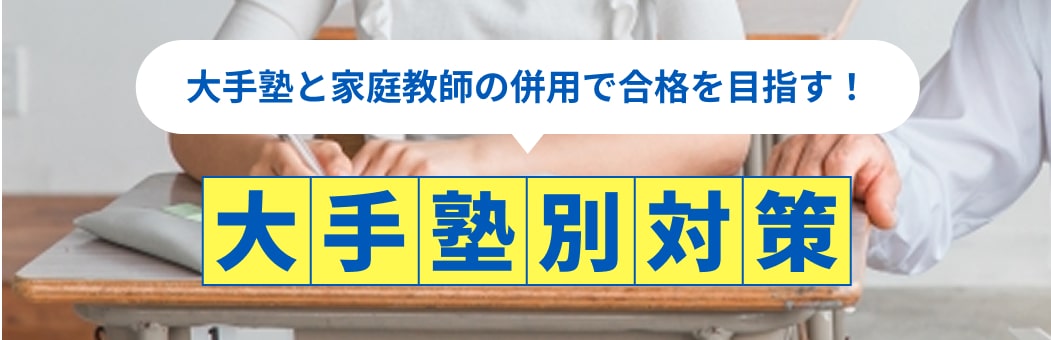
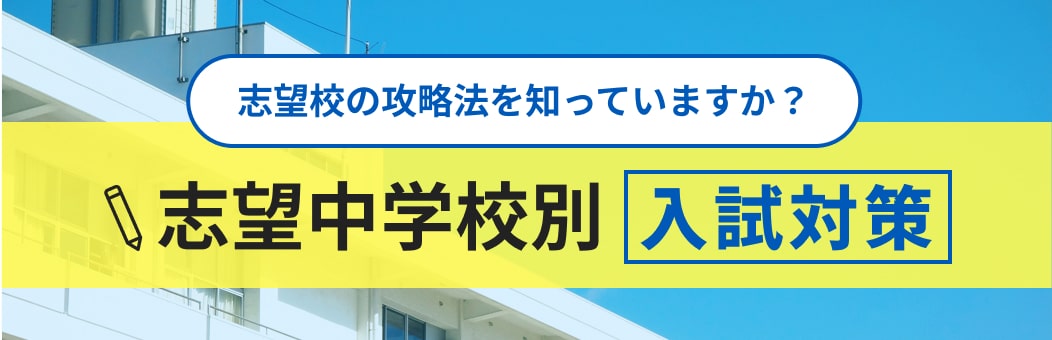
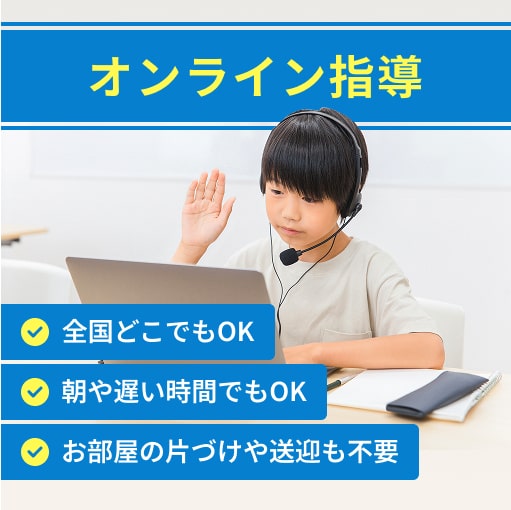
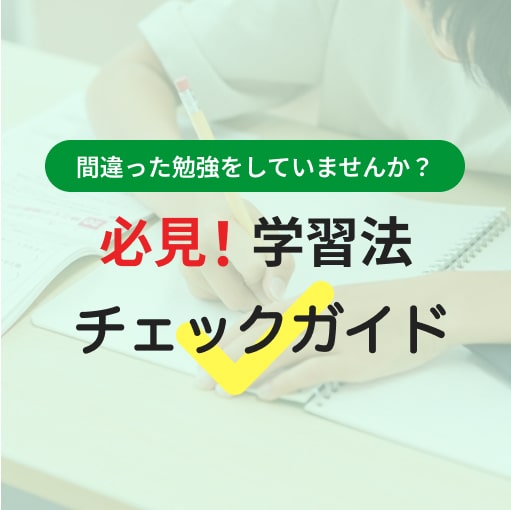
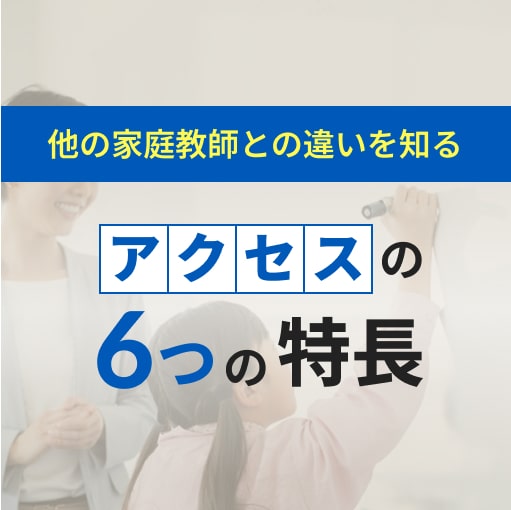
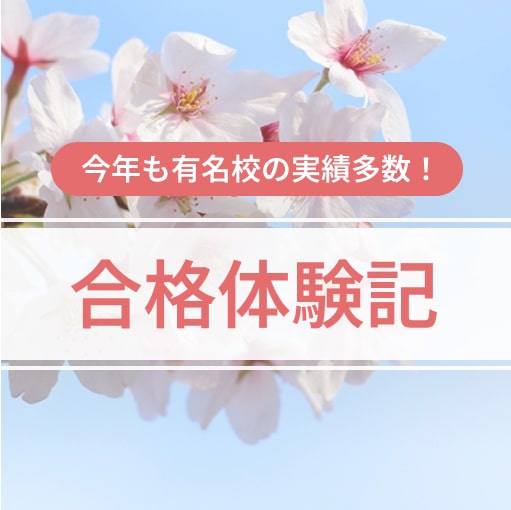
明治大学付属明治中学校合格に必要なのは、「計算力」、「読解・分析・思考力」「記述・表現力」です。
オーソドックスな問題をきちんと解くことのできる基礎力を付けた上で、考えて解ける応用力が求められています。
長文をスピーディーかつ正確に読む「読解力」、読解したものをもとに分析し意見を記す「記述力」、「論理的思考力」を使い、正解を生み出す「計算力」、複数の資料を分析して考え、考えをまとめる「表現力」等様々な力が付くように、過去問を使いながら、アクセスの講師と一緒に対策を進めていきましょう。