
| 学校名 | 國學院久我山中学校 |
|---|---|
| 共学・別学 | 男女別学 |
| 住所 | 〒168-0082 東京都杉並区久我山1丁目9−1 |
| ホームページ |
総合難易度:★★★☆☆
- 算数難易度:★★★☆☆
- 国語難易度:★★★☆☆
- 理科難易度:★★★☆☆
- 社会難易度:★★★☆☆
國學院久我山中学校について
國學院久我山中は、東京都杉並区にある私立中高一貫校です。
男子部と女子部に分かれた男女別学ですが、学校行事や部活動は男女合同で行われることも多いです。
國學院大學の付属校で、優先入学推薦制度がありますが、卒業生の大半は他大学へ進学しています。東大をはじめとする国公立大学、早慶上理、医学部医学科等に多数の合格者を出しており、進学校としての特色が強いといえるでしょう。
入試の特長
①算数は応用問題で差が付く。
②理科・社会では基本~標準レベルでの網羅的知識が要求される。
③国語・社会では記述問題が多い。
科目別の分析
科目別出題形式・タイプ分析
| 科目 | 配点 | 時間 | 問題数 | 難易度 | 記述・要途中式 | 要思考力問題率 | 難問出題率 | 出題タイプ | 合格最低ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 50分 | 普通 | 普通 | 30% | 25% | 5% | AB | 64% |
| 算数 | 100点 | 50分 | 普通 | 普通 | 25% | 30% | 10% | AB | 64% |
| 理科 | 50点 | 40分 | 普通 | 普通 | 0% | 30% | 10% | AB | 64% |
| 社会 | 50点 | 40分 | 普通 | 普通 | 18% | 10% | 0% | AB | 64% |
出題タイプの解説
- Aタイプ全体の9割以上が知識や公式を知っていて、その活用法が分かっていれば解ける出題の学校。
- Bタイプ全体の3割以上が正解を出すために、思考力や発想力を必要とする問題の学校。
- ABタイプ全体の1割から3割がBタイプ(正解を出すために思考力や発想力を必要とする問題)の学校。
科目別出題傾向
| 科目 | 出題されやすい単元・形式 |
|---|---|
| 国語 |
●小説・物語文 ●論説・説明文 ●漢字の読み書き ●言葉の知識(熟語、敬語、言葉の意味など) |
| 算数 |
●計算問題 ●特殊算(つるかめ算) ●約束記号 ●比と割合 ●速さ(旅人算) ●平面図形(求積、点の移動) |
| 理科 |
●物理・化学・生物・地学分野から幅広く出題 ●資料(グラフ・表など)を題材にしたテーマが多い |
| 社会 |
●日本の地理 ●日本の歴史 ●公民 ●時事問題 |
國學院久我山中学校の科目別攻略方法
国語の攻略方法
国語の出題傾向と学習方法
大問数3題(小問数は約25問)の問題構成でなっている。
大問1・2では読解問題が出題され、論説・説明文と小説・物語文から1題ずつ出題されることが多い。大問3では、漢字の読み書きや言葉の知識問題が出題される。
國學院久我山の国語の特徴として挙げられるのは、「記述問題の多さ」と「知識問題の多さ」の2点だろう。
記述問題が小問総数に占める割合は少ないけれど、配点で約3割ぐらい占めており、記述力がなければ合格点に届くのは難しいだろう。記述問題の演習量を意識的に増やして万全を期したい。
また、2点目の知識問題の多さだが、こちらも配点でいうと約3割(約30点分)を占めている。記述問題で満点を取ることはなかなか難しい分、この知識問題ではできるだけ満点を取れるように対策を講じておきたい。毎日漢字や言葉の知識を補充する習慣をつけることが必要だろう。
試験で高得点をとるポイント
まずは大問3の知識問題を速やかに解く。
その後、大問1・2の論説・説明文と小説・物語文のうち、得意な方から順次解いていくのが良いだろう。
小問数は少ないが、記述問題が多い分、時間に余裕があるわけではないので、時間がかかりそうな問題は一旦飛ばすことも必要になってくる。時間配分には十分意識したい。
算数の攻略方法
算数の出題傾向と学習方法
大問約4題(小問数は約20問)の問題構成となっている。
大問1では計算問題、大問2では小問集合が出題される。この2題で配点の半分以上を占めており、なおかつ基本問題が中心となっているので、この部分は満点近い得点を取りたい。計算問題のミスをなくし、小問集合をしっかりと演習しておく必要があるだろう。
また、後半の大問3・4では応用問題が出題されるが、算数の得点の差はここで生まれるだろう。頻出分野を中心に、応用レベルの問題にもしっかりと取り組んでおきたい。
また、最後の大問では考え方を記述する欄がある。答えまで出なくても、考え方を記入すれば部分点がもらえる可能性が高い。日ごろの学習の際から、ノートにしっかりと途中過程を書く習慣をつけておこう。
試験で高得点をとるポイント
まずは大問1・2の計算問題・小問集合を素早く解く。この2題は基本レベルではあるが、ここでの失点は致命的になりかねない。ミスのないように注意したい。
大問1・2が終わったら、後半の大問3・4に一旦目を通し、手の付けやすい方から解いていく。目安としては、大問3・4では半分以上得点したいところである。
理科の攻略方法
理科の出題傾向と学習方法
大問数5題(小問数30問)の問題構成で、物理・化学・生物・地学の全分野から出題されています。
解答形式は、記号選択、適語記入が大半で、計算問題も数問出題されます。
出題テーマが年度によってバラバラなので、頻出分野に絞って勉強するのではなく、幅広く網羅的に学習していることが重要です。とはいえ、細かい知識まで網羅的に覚えるというよりは、基本~標準的な事項を網羅的に学んでいることが要求されています。
また、國學院久我山の理科の特徴として挙げられるのは、実験や観察を題材にした問題が多い点です。日ごろの学習で、知識を単純に覚えるのではなく、実験や観察に紐づいた知識として学習することが、國學院久我山対策として適していると言えるでしょう。
試験で高得点をとるポイント
まず、大問すべてを一通り見たのち、得意分野の問題から順次解いていくのが良いでしょう。
全体的に基本レベルの出題が多く、時間的にも無理のない出題なので、あわてる必要はありません。しかし、分からない問題で時間を浪費することは大きな失点につながるので、分からない問題・時間のかかりそうな問題があれば、後回しにして時間の浪費を防ぐことも重要です。
社会の攻略方法
社会の出題傾向と学習方法
大問数3題(小問数約25問)という問題構成になっている。
大問別にみると、大問1は公民と時事、さらに日常的な内容を含んだ総合問題、大問2は地理、歴史を合わせた総合問題、大問3は歴史の中でも時代の流れを問うような問題が出題される傾向がある。そのため、まずは地歴公民3分野を網羅的に学習することが必要だろう。
また、全体を通して資料(グラフ、図、写真)を用いた出題が多いので、資料集などにもしっかりと目を通しておきたい。
解答形式は記号選択・適語記入だけでなく、記述問題が多い点も國學院久我山の特徴と言えるだろう。記述問題は、「説明」と「理由・原因」を問う問題が多いので、知識を覚える際は、用語を覚えるだけでなく、「用語の内容を自分で説明できるようにしておくこと」と「社会的事象の理由・原因を学んでおくこと」の2つが重要だろう。
試験で高得点をとるポイント
まずは一通り問題を見たのち、手の付けやすそうな問題から順次解いていく。
その際、記述問題で時間がかかりそうであれば、まずは記号選択・適語記入を速やかに解いて、その後腰を据えて記述問題に取り込むのが良いだろう。
対策まとめ
お子さま一人ひとりに合った対策を、今から始めましょう
100人いれば100通りの受験。中学受験の対策は、お子さま一人ひとりで大きく変わります。
まずは現在の学習状況や目標を把握し、限られた時間の中でベストな方法をご提案いたします。
まずは無料相談で、お悩みをお聞かせください。今後の方向性を一緒に見つけましょう。
無料相談もこちらお問い合わせください

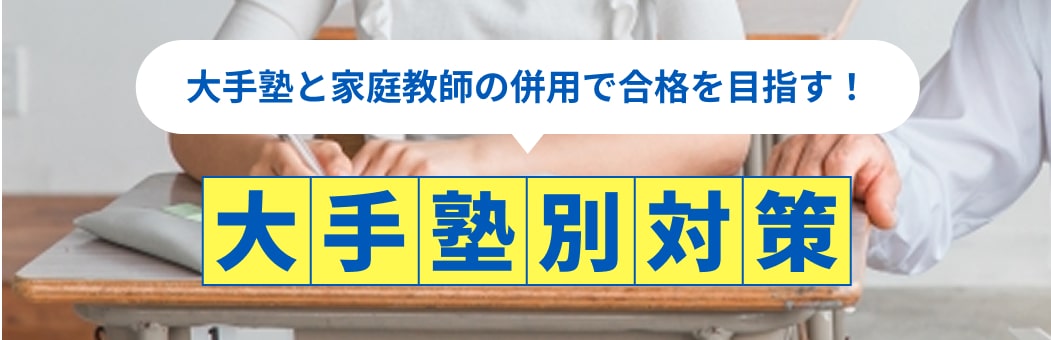
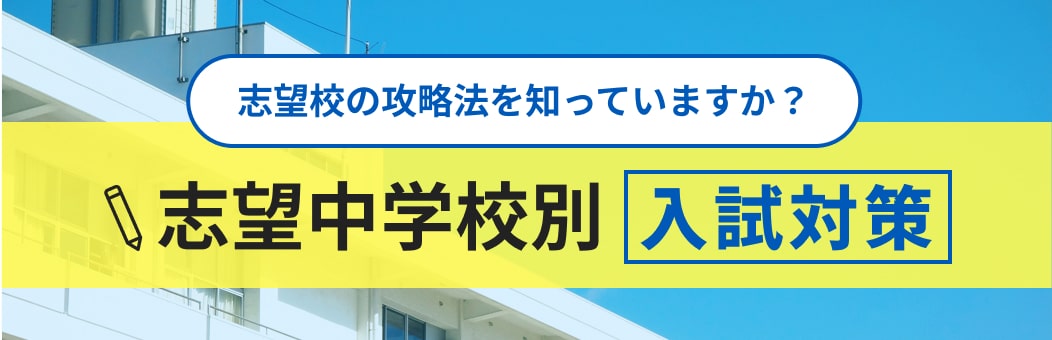
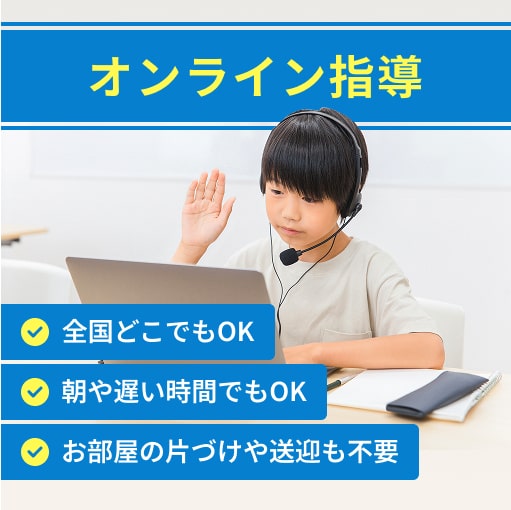
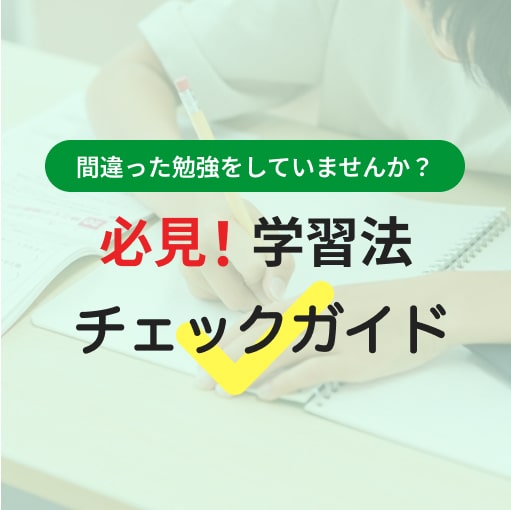
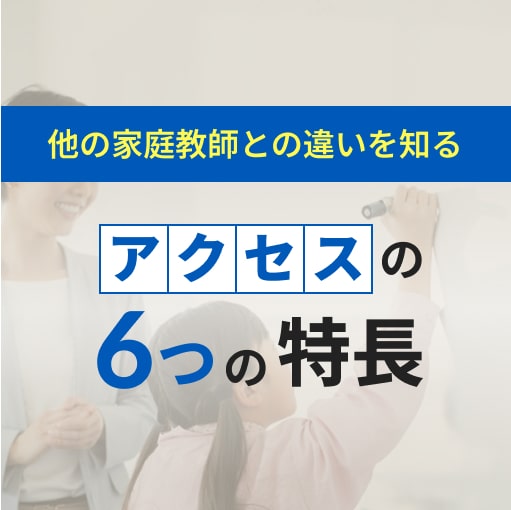
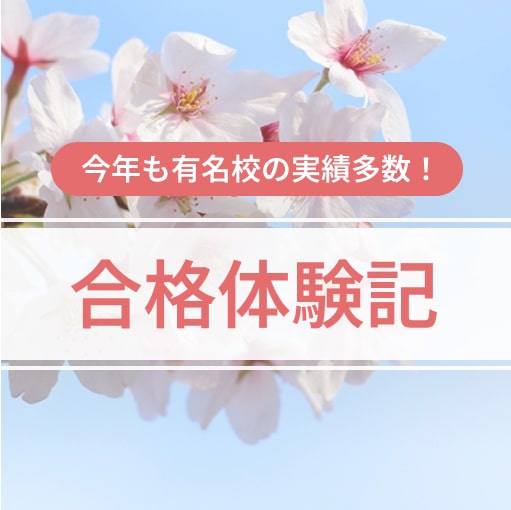
國學院久我山中合格に必要なのは、「基本~標準レベルでの網羅的知識」、「算数の応用力」、「記述力」の3つです。
まず、4科目を通して基本~標準レベル、かつ幅広いテーマでの出題が中心であるため、全科目において標準レベルまでの内容を網羅的に学んでいなければ合格は厳しいと言えるでしょう。
その上で、算数では応用問題も出題され、そこで最も差が付きやすくなっています。算数に関しては応用レベルの内容まで学んでおく必要があるでしょう。
最後に、国語と社会では記述問題の比率が高く、配点ベースで言えば国語では約30%、社会では約20%を記述問題が占めています。記述問題が苦手という受験生が昨今多いですが、記述問題に対して苦手意識を持ったまま試験に挑むのでは合格最低点に届くのはかなり厳しくなってしまいます。記述力の強化は必要不可欠と言えるでしょう。