
| 学校名 | 中央大学附属中学校 |
|---|---|
| 共学・別学 | 共学校 |
| 住所 | 〒184-0015 東京都小金井市貫井北町3丁目22−1 中央大学附属高等学校 |
| ホームページ |
総合難易度:★★★☆☆
- 算数難易度:★★★☆☆
- 国語難易度:★★★★☆
- 理科難易度:★★★★☆
- 社会難易度:★★★☆☆
中央大学附属中学校について
中大附属中は東京都小金井市にある中高一貫の共学校です。
「個人の尊厳を尊重し、自由に個性を伸ばす」をもっとも重要な教育方針としており、そのため校則は存在せず、非常に自由な校風です。
卒業生の約9割が中央大学へと進学していますが、他大への進学者もおり、早慶上理といった上位校への進学者も多いのが特徴です。
入試の特長
①読解力を問われる(特に国語・理科)。
②勉強と生活の接点を問う様な本質的な問題が多い。
③問題のレベル自体は、基礎~標準レベルのものが大半。
科目別の分析
科目別出題形式・タイプ分析
| 科目 | 配点 | 時間 | 問題数 | 難易度 | 記述・要途中式 | 要思考力問題率 | 難問出題率 | 出題タイプ | 合格最低ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 50分 | やや多 | やや難 | 0% | 5% | 5% | A | 58% |
| 算数 | 100点 | 50分 | 普通 | 普通 | 0% | 20% | 10% | AB | 58% |
| 理科 | 60点 | 30分 | やや多 | やや難 | 0% | 40% | 15% | AB | 58% |
| 社会 | 60点 | 30分 | 普通 | 普通 | 10% | 5% | 5% | A | 58% |
出題タイプの解説
- Aタイプ全体の9割以上が知識や公式を知っていて、その活用法が分かっていれば解ける出題の学校。
- Bタイプ全体の3割以上が正解を出すために、思考力や発想力を必要とする問題の学校。
- ABタイプ全体の1割から3割がBタイプ(正解を出すために思考力や発想力を必要とする問題)の学校。
科目別出題傾向
| 科目 | 出題されやすい単元・形式 |
|---|---|
| 国語 |
●漢字の読み書き ●小説・物語文 ●論説・説明文 |
| 算数 |
●計算問題 ●割合と比(濃度) ●速さ(旅人算) ●立体図形(体積、表面積、回転、水そう) |
| 理科 |
●物理・化学・生物・地学分野から幅広く出題 ●小学校で習わない内容をリード文を読んで解く問題が頻出 |
| 社会 |
●日本の地理 ●日本の歴史 ●公民 ●時事問題 |
中央大学附属中学校の科目別攻略方法
国語の攻略方法
国語の出題傾向と学習方法
大問2題(小問数は50問前後)の構成で、大問1が小説・物語文(漢字の書き取りを含む)、大問2が論説・説明文となっている。また、年度によっては随筆文が出題されることもある。
設問の難易度自体は基本的なレベルだが、大問1の小説・物語文の文章量が非常に多いため、難易度が上がっている。設問に答える前段階として、長文でもしっかりと読み切る力が求められる。日ごろから文章量の多い問題に取り組んだり、好んで読書をするなどして、長文に対する体力をしっかりと付けておくことが必要不可欠だろう。
また、必ず漢字の書き取り問題が出題されるが、標準的なレベルの漢字ばかりなので、毎日しっかりと漢字の練習をするなどして、漢字問題では必ず満点を取れるようにしておきたい。
試験で高得点をとるポイント
小説・物語文が得意であれば大問1から、論説・説明文が得意であれば大問2から手を付ける。
その際、全体的に文章量が多く時間的な余裕はあまりないので、しっかりと時間配分を決めた上で解き始めること。時間配分を決めずに流れに任せて解くと、最後まで解けずに大きく失点してしまう可能性があるので注意が必要だ。
算数の攻略方法
算数の出題傾向と学習方法
大問5題(小問数は約25問)の構成で、解答形式は途中過程などを書く欄はなく、解答のみを記入する形式になっている。
大問1で計算問題・小問集合が、大問2以降では独立した問題が出題される。
出題レベルとしては、思考を必要とする問題も出題されるもののオーソドックスな内容が非常に多いため、典型問題を扱った問題集を1冊完璧に仕上げれば合格点を取ることは難しくない。まずは1冊、しっかりと習得することが合格への近道となるだろう。
また、先述のとおり途中過程を書く欄がないので、ミスをいかに減らすかもポイントになる。ミスノートを作るなどして、自分のミスしやすいポイントをしっかりと把握し、回避する術を身に付けた状態で試験に望みたい。
試験で高得点をとるポイント
まずは大問1の計算問題・小問集合を素早く解く。
その後、大問2以降に一通り目を通して、手を付けられそうな問題から順次解いていく。
途中過程を書く欄がないため、ミスは命取りになる。しっかりと見直し時間も考慮した時間配分をあらかじめ決めて試験に臨みたい。
理科の攻略方法
理科の出題傾向と学習方法
大問数4題(小問数は約25問)の構成で、解答形式は記号選択・適語記入が中心ではあるものの、計算問題や作図問題も数問出題される。
中大附属の理科の特徴としては、小学校では習わない内容をリード文を読んで解くという問題が頻出する点が挙げられる。平成25年度入試で言うと、高校で習う「ネフロン」(生物分野)、「化学結合・イオン」(化学分野)といったテーマでの出題があるが、これは高校レベルまでの学習を求めているのではなく、いかにリード文から内容を学べるかという、いわば読解力を問う問題だと言える。
初見のものでも説明をしっかりと読み、そこからポイントを正確に捉え、そのポイントを使って思考し解答するという訓練が非常に大切になってくる。類似問題を出す学校の過去問も使いながら、その力を養う必要があるだろう。
また、全体を通して実験や日常生活に関係させた出題も目立つ。日ごろから、身の回りの科学に興味を持ち、自分なりに考察する習慣を身に付けたい。
試験で高得点をとるポイント
30分で25問だが、読解を必要とする問題があるため、時間的な余裕はあまりない。
まずは一通り問題に目を通し、手の付けやすい問題から素早く解いていく。
その後、残りの時間を使って読解を必要とする問題を解く。
先述の通り、時間に余裕はないので、時間を常に意識しながら解くことが大事だ。
社会の攻略方法
社会の出題傾向と学習方法
大問2題(小問数約30問)という問題構成で、解答形式は記号選択・適語記入が中心だが、記述問題が数問出題される。
特徴としては、新聞記事や会話文を題材に、一つの大問の中に地理・歴史・公民・時事の複数分野を内包させている点であろう。日ごろの学習の際に、それぞれの分野を独立させて捉えるのではなく、横断的なつながりを意識しながら学習する必要がある。また、新聞を読むことは時事問題対策だけでなく、上記のような出題傾向の対策にもなるので有効だ。
とはいえ、出題レベルとしては基本~標準レベルが中心なので、抜けもれなく万遍なく学習しておけば合格点を取ることは難しくない。
また、漢字指定などもあるので、知識内容を覚える際は漢字まで正確に覚えておきたい。
試験で高得点をとるポイント
分からない問題は一旦飛ばして、まずは解けそうな問題から順次解いていく。
その後、一旦飛ばした問題に戻り、解答していくのが良いだろう。
対策まとめ
お子さま一人ひとりに合った対策を、今から始めましょう
100人いれば100通りの受験。中学受験の対策は、お子さま一人ひとりで大きく変わります。
まずは現在の学習状況や目標を把握し、限られた時間の中でベストな方法をご提案いたします。
まずは無料相談で、お悩みをお聞かせください。今後の方向性を一緒に見つけましょう。
無料相談もこちらお問い合わせください

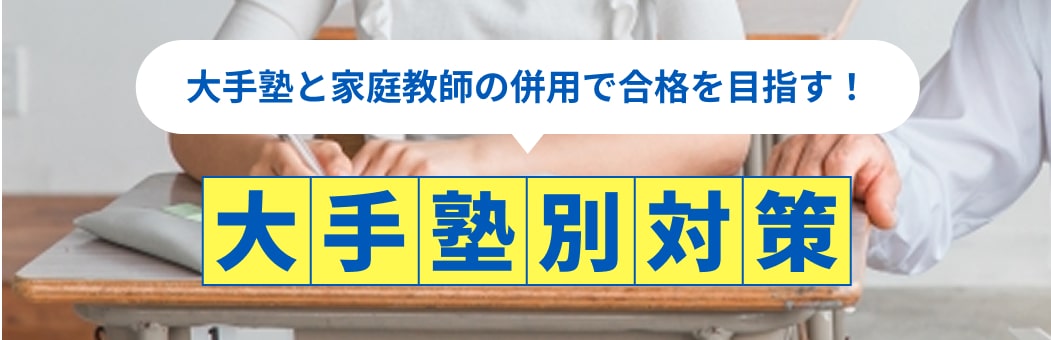
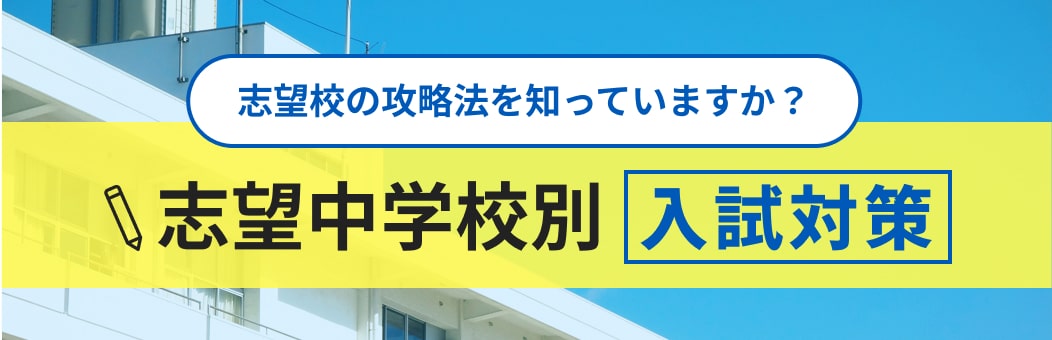
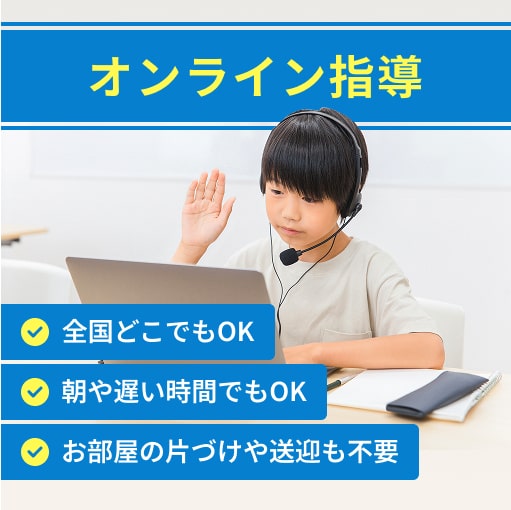
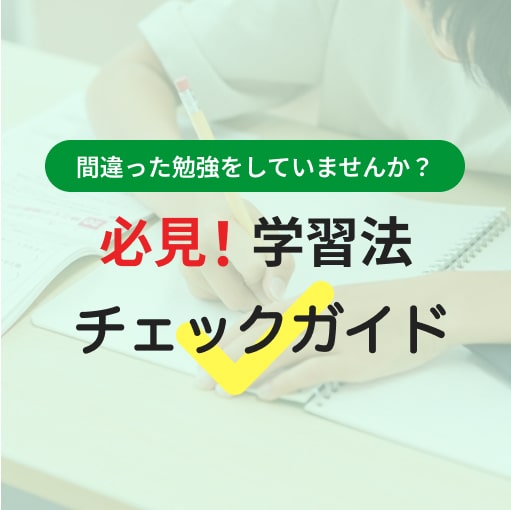
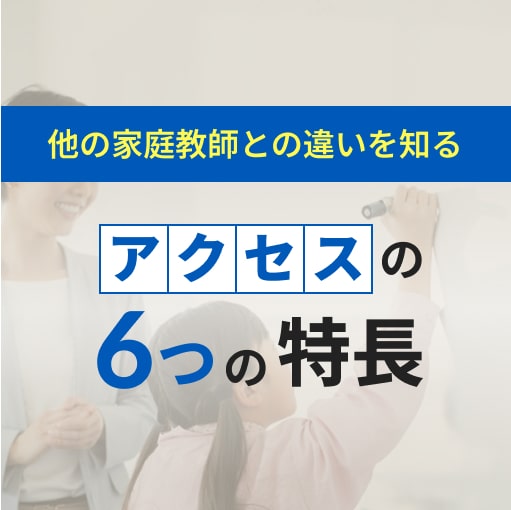
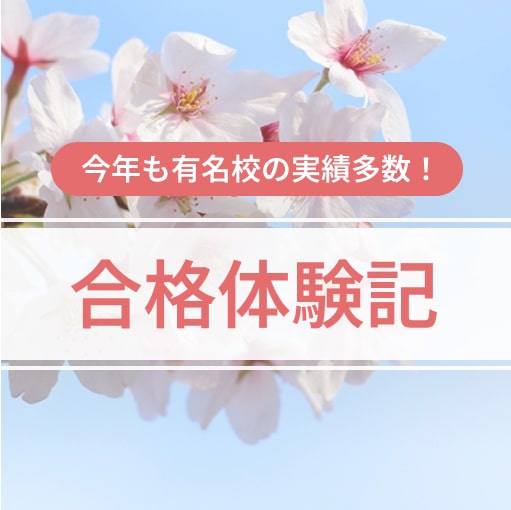
中大附属中合格に必要なのは、「基本レベルの知識の網羅性」、「読解力」、「勉強と身の回りのことの関連性を意識すること」の3つです。
まず、4科目を通して基礎~標準的な内容からの出題が大半を占めているため、基本レベルの知識を正確かつ網羅的に学んでいることが、合格に必要不可欠な条件となります。
また、国語では文章量の多い読解問題が出題され、理科では未習内容をリード文を読んで解く問題が出題されるため、読解力が非常に重要になってきます。前者の場合は、「早く正確に読む読解力」、後者の場合は「未習内容を即座にキャッチアップする読解力」と言えるでしょう。
最後に、特に理科・社会においては、「受験勉強」という枠組みから外れて、「勉強(学問)と生活の接点」をいかに意識しているかを問う問題が出題されています。そのため、ただ受験勉強と割り切って機械的に学ぶのではなく、勉強と生活の関連性を意識して日ごろから学習する姿勢が問われていると言えるでしょう。