
| 学校名 | 城北中学校 |
|---|---|
| 共学・別学 | 男子校 |
| 住所 | 〒174-8711 東京都板橋区東新町2-28-1 |
| ホームページ |
総合難易度:★★★★☆
- 算数難易度:★★★★☆
- 国語難易度:★★★★☆
- 理科難易度:★★★★☆
- 社会難易度:★★★★☆
城北中学校について
城北中は、東京都板橋区にある中高一貫の難関男子校の一つです。
20年ほど前から中高6年を2年ごとの3期に分けており、始めの2年を基礎期、次の2年を練成期、最後の2年を習熟期としており、各時期に応じた教育が行われています。
その結果、大学進学にも大きな成果が表れており、進学実績は右肩上がりに推移しています。
卒業生の多くが東大、東工大、一橋大、早慶上智理科大、医学部など最上位レベルの大学へと進学しており、進学校としての地位を確立しています。
入試の特長
①基本・標準レベルの完成は最低条件。
②応用レベル(論理的思考力・読解力)の有無で差が付く。
科目別の分析
科目別出題形式・タイプ分析
| 科目 | 配点 | 時間 | 問題数 | 難易度 | 記述・要途中式 | 要思考力問題率 | 難問出題率 | 出題タイプ | 合格最低ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 50分 | 標準 | やや難 | 60% | 40% | 25% | B | 65% |
| 算数 | 100点 | 50分 | 標準 | やや難 | 0% | 40% | 40% | A | 65% |
| 理科 | 70点 | 40分 | 標準 | やや難 | 25% | 35% | 15% | AB | 65% |
| 社会 | 70点 | 40分 | やや多 | やや難 | 0% | 15% | 15% | AB | 65% |
出題タイプの解説
- Aタイプ全体の9割以上が知識や公式を知っていて、その活用法が分かっていれば解ける出題の学校。
- Bタイプ全体の3割以上が正解を出すために、思考力や発想力を必要とする問題の学校。
- ABタイプ全体の1割から3割がBタイプ(正解を出すために思考力や発想力を必要とする問題)の学校。
科目別出題傾向
| 科目 | 出題されやすい単元・形式 |
|---|---|
| 国語 |
●小説・物語文 ●漢字 |
| 算数 |
●計算(四則計算、分数、虫食い算) ●仕事算 ●速さ(通過算、流水算、ダイヤグラム) ●平面図形(移動) ●空間図形(切断) |
| 理科 |
●物理分野(力のつり合い、音、電流、計算問題) ●化学分野(水溶液、金属、気体、計算問題) ●生物分野全般 ●地学分野全般 |
| 社会 |
●日本の地理 ●日本の歴史 ●公民 |
城北中学校の科目別攻略方法
国語の攻略方法
国語の出題傾向と学習方法
平成29年度より出題形式が変更された。
従来の大問4問構成から、小説・物語文1題、漢字問題1題という大問2題構成となり、配点比率も9:1となっている。
読解問題は一万字ほどで、解答形式は、記述形式、選択形式半々で構成されている。文中の主人公や登場人物の心情を、的確に読み解く力が求められている。 記述問題は長文記述、短文記述があり、配点も高いので、しっかりと対策を講じておきたい。
選択問題は選択肢が多く、さらに単純な選択ではなく複雑なものが多いため、文章を深く読み、しっかりと内容を把握する力が必要になってくる。 日ごろの読解演習の際に、ただ単に読んで問題を解くのではなく、文章を読んだ後に自分なりに図でまとめるといった作業をすることで論理的読解力を磨きたい。
また、漢字は得点源にするために、日ごろからの学習習慣は欠かせない。 毎日時間を決めて、少しずつ着実に習得していきたい。
試験で高得点をとるポイント
漢字問題を先に解き、着実に得点源としたい。
長文なので、場面転換、心情変化をつかみながら、読み進めて欲しい。
問題文で聞かれていることを理解し、丁寧に答えていくことが得点を積み上げていくのに必要だ。
算数の攻略方法
算数の出題傾向と学習方法
大問数は5題から6題で、小問数は15問ほどと一見少なく見えるが、思考力を問う難度の高い問題も多いため、時間的な余裕はない。
大問1,2では基本から標準レベルの計算問題と小問集合が出題されるが、この2題の配点が非常に高いので、ここでできるだけ満点に近い点を取ることが高得点を目指す上で最も効率的である。
大問3以降では思考力を問う難度の高い問題が多いが、頻出分野がはっきりしているので対策は講じやすい。「仕事算」、「速さ(通過算、流水算、ダイヤグラム)」、「図形(移動、切断)」が頻出なので、これらの分野を重点的に演習し、高得点を目指したいところである。
試験で高得点をとるポイント
まず、大問1、2を素早く、かつケアレスミスのないように解く(完答を目指す)。
その後、大問3以降に手を付けていくが、確実に点を重ねるためには、(1)を完答することを意識したい。
(1)を完答したら、(2)以降で解けそうな問題をこなし、さらなる加点を目指す。
理科の攻略方法
理科の出題傾向と学習方法
大問数は5~6題で、物理・化学・生物・地学の4分野から出題される。
実験・観察に基づく問題、物理・化学の計算問題の比重が多く、ここで点差が付きやすいので、対策をしっかり講じておきたい。グラフ作成、作図なども出題されている。物理分野では「力学(てこ・滑車・ばね)」、「電磁気(電流・磁界)」、化学分野では「水溶液(溶解度)」、「気体」、「燃焼」などが頻出なので、これらに対しては得意分野になるくらいに何度も演習を重ねておきたい。
また、知識問題は生物・地学分野に偏っているので、生物・地学の知識は網羅的に習得しておこう。生物の絵を描く問題なども出題されているので、知識を覚えるだけでなく、普段から興味を持って観察することを心がけて欲しい。
試験で高得点をとるポイント
まずは試験問題全てを俯瞰し、基本問題(知識問題)と応用問題(計算問題)を見極める。
その後、知識問題をすみやかに解き、計算問題に十分な時間を割けるようにする。
社会の攻略方法
社会の出題傾向と学習方法
大問数は3題(小問数は50問程)で、地理・歴史・公民分野から1題ずつという構成になっている。
全体を通して記述・作図問題はないものの、約50問を40分で解かなくてはならず時間的に余裕がないため、スピーディーに問題をこなす力が必要不可欠となる。 出題の傾向はあまり変わらないので、過去問をなるべく多く解いてパターンに慣れておくと良い。地図・グラフ・表の読解問題は、頻出だ。
歴史も時代の流れや資料にも注目して、理解し、確認しておくことが必要だ。
公民だけでなく、地理でも時事がらみの問題が出されるので、日頃から新聞やニュースをチェックして、関連事項を確認しておこう。
試験で高得点をとるポイント
記述・作図問題はなく短答式の問題が中心であり、なおかつ問題数が多いので、スピーディーに解いていくが重要だ。
その際の注意点として、少し考えないと答えを出せなそうな問題は一旦飛ばして後回しにすること。
時間の浪費は致命的になりかねない。
対策まとめ
お子さま一人ひとりに合った対策を、今から始めましょう
100人いれば100通りの受験。中学受験の対策は、お子さま一人ひとりで大きく変わります。
まずは現在の学習状況や目標を把握し、限られた時間の中でベストな方法をご提案いたします。
まずは無料相談で、お悩みをお聞かせください。今後の方向性を一緒に見つけましょう。
無料相談もこちらお問い合わせください

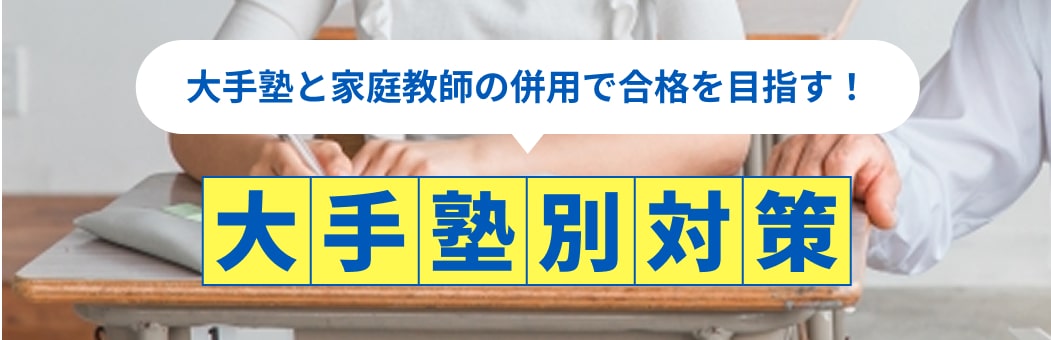
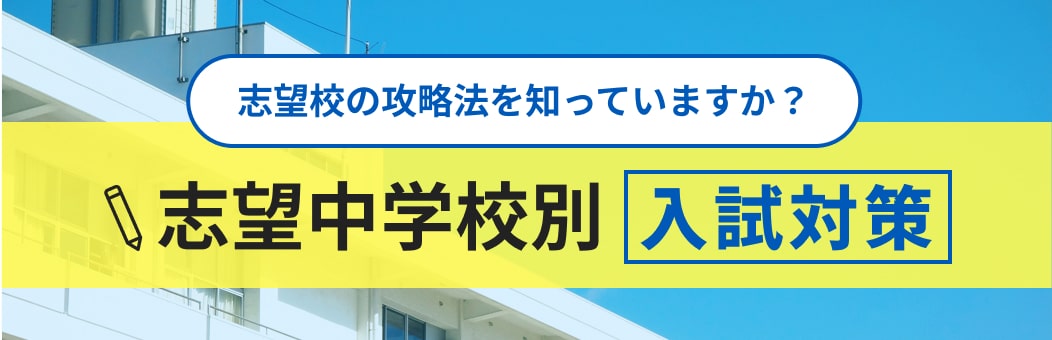
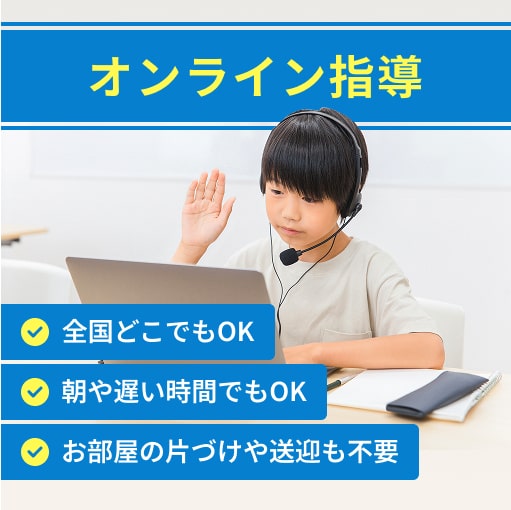
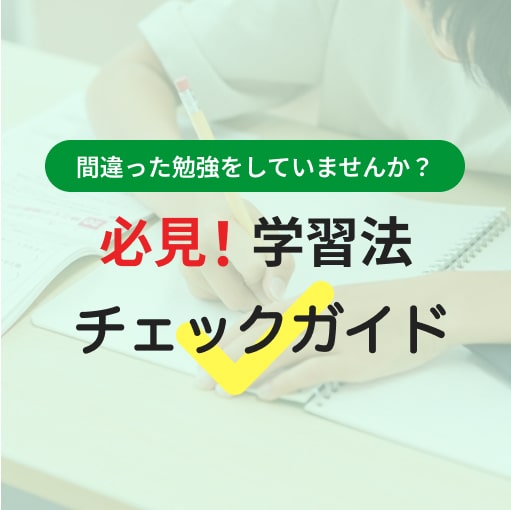
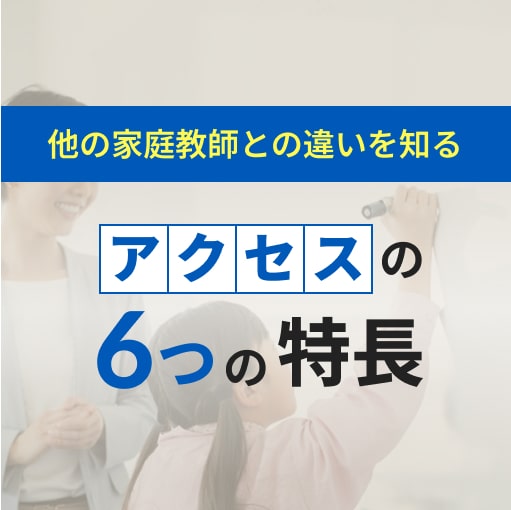
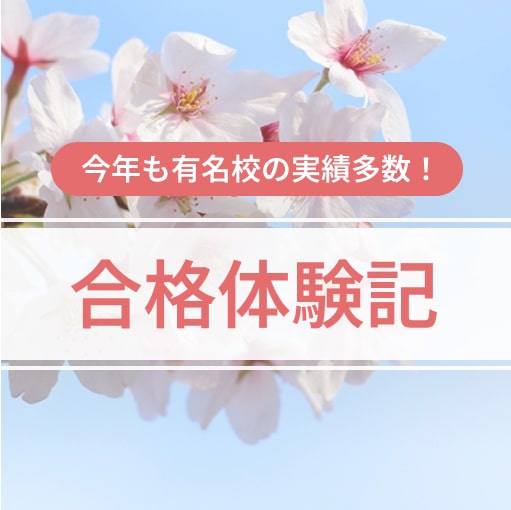
城北中合格に必要なのは、「基本・標準レベルの完成度」、「論理的思考力・読解力」の2つです。
まず、城北では基本・標準レベルの問題を確実に正解した上で、応用問題でいかに得点できるかが合否の分かれ目になってきます。そのため、「基本・標準レベルの完成度」は合格のための最低条件になります。
そしてその最低条件をクリアした上で、合否の分かれ目となるのが応用力です。これは具体的に言えば「論理的思考力」と「論理的読解力」の2つで、この2つが習得できていなければ最も差のつく算数・国語での得点確保につながりません。
以上のように、土台としての「基本・標準レベルの完成度」、そしてそれを習得した上でそれを使いこなすという「応用力(論理的思考力・読解力)」が要求されており、非常に完成度の高い生徒を選考したいという学校側の意図が読み取れます。