
| 学校名 | 中央大学横浜中学校 |
|---|---|
| 共学・別学 | 共学校 |
| 住所 | 〒224-0014 神奈川県横浜市都筑区牛久保東1丁目14−1 |
| ホームページ |
総合難易度:★★☆☆☆
- 算数難易度:★★☆☆☆
- 国語難易度:★★☆☆☆
- 理科難易度:★★☆☆☆
- 社会難易度:★★☆☆☆
中央大学横浜中学校について
中央大学横浜中学校は中央大学附属の学校です。
2010年に中央大学の附属校になったばかりで、附属校としてはまだ歴史の浅い学校です。2013年には山手から港北ニュータウンへキャンパスが移転しました。
最近は人気も急上昇しており、それに伴いレベルもアップしています。問題は基本的な問題が多く難問・奇問の類は出題されませんが、合格するためには高得点が必要なため十分な練習が必要です。
また解答時間のわりに問題数は多く、手際の良い処理が要求されます。
入試の特長
①算数でも途中式や考え方を記述させる問題が出題される。
②国語は選択問題が中心で抜き出しでない記述問題はあまり多くは出題されない。
③理科・社会は試験時間の割に問題数が多い。
科目別の分析
科目別出題形式・タイプ分析
| 科目 | 配点 | 時間 | 問題数 | 難易度 | 記述・要途中式 | 難問出題率 | 出題タイプ | 合格最低ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 150点 | 50分 | やや多 | 標準 | 10% | 0% | A | 70% |
| 算数 | 150点 | 50分 | 標準 | やや易 | 60% | 0% | A | 75% |
| 理科 | 100点 | 35分 | やや多 | 標準 | 0% | 0% | A | 75% |
| 社会 | 100点 | 35分 | 多い | 標準 | 0% | 0% | A | 75% |
出題タイプの解説
- Aタイプ全体の9割以上が知識や公式を知っていて、その活用法が分かっていれば解ける出題の学校。
- Bタイプ全体の3割以上が正解を出すために、思考力や発想力を必要とする問題の学校。
- ABタイプ全体の1割から3割がBタイプ(正解を出すために思考力や発想力を必要とする問題)の学校。
科目別出題傾向
| 科目 | 出題されやすい単元・形式 |
|---|---|
| 国語 |
●物語文、小説文 ●説明文・論説文 ●漢字の読み書き ●ことばの知識 |
| 算数 |
●四則計算 ●数の性質 ●比と割合 ●平面図形 ●旅人算、通過算、平均算、相当算 |
| 理科 |
●物理(てこ、ばね、滑車・輪軸) ●化学(水溶液) ●生物(植物、人体) ●地学(天体) |
| 社会 |
●地理 ●歴史 ●政治(総合、三権のしくみ) |
中央大学横浜中学校の科目別攻略方法
国語の攻略方法
国語の出題傾向と学習方法
読解問題は選択問題が中心になるので文章を正確に読み取る練習が必要。抜き出し問題も良く出題されるので練習しておく。記述問題対策としてはポイントを押さえた表現ができるようにすることが重要。知識問題は漢字の読み書き、熟語、ことばの知識を中心にきちんと覚えておく。
試験で高得点をとるポイント
まず知識問題から解いていき、長文問題は文章が長いので手早く読み込み、選択問題や抜き出し問題から手早く片付け、記述問題に時間を割けるようにする。
算数の攻略方法
算数の出題傾向と学習方法
四則計算、平面図形、数の性質、比と割合、旅人算を中心に他の特殊算も出題されるので、基本的な問題や典型的な問題は早く正確に解ける練習が必要。途中式や計算を書かせる問題も出題されるのできちんと途中式や計算を書き残しておく習慣をつける。
試験で高得点をとるポイント
問題の難易度を素早く見抜き、解き易いものから手際よく解いてゆく。計算ミスが無いように正確に処理する。
理科の攻略方法
理科の出題傾向と学習方法
どの分野から出題されても大丈夫なように幅広く基本的な知識を身につけておくことが肝心。
実験結果や図やグラフのデータから読み取り考察する練習も必要。計算問題も結構出題されるので練習をしておく。
試験で高得点をとるポイント
選択問題からどんどん手際よく解いていき、計算問題にも時間が取れるようにする。
社会の攻略方法
社会の出題傾向と学習方法
どの分野も幅広く基本的な知識を身につけておくことが重要。
総合問題形式で出題されるのでその出題形式に慣れておくことが肝心。
時事問題や環境問題への対策もおろそかにしない。
試験で高得点をとるポイント
問題数が多いので解きやすい問題から手際よく解いていく。
プロ講師による合格までの指導体験記
プロ講師による指導実例
私がSさん(仮名)の指導を開始したのは、Sさんが日能研での新6年生になって間もなくのことでした。
指導開始時点で既にSさんは中大横浜中学を第一志望校に決めていましたが、その時点でのSさんの成績は4科目総合偏差値が40代の後半で、このままではとても中大横浜には届きそうもないのが現状でした。
でも私はSさんのひたむきで真面目な態度から、この生徒ならきっとうまくいく、と直感的に確信したのです。そしてそのSさんの想いに応えてあげなければと使命感に燃えたことを今でもよく覚えています。
プロ講師は算数の弱点をどう対策するか?
Sさんは算数を特に苦手としていましたので、まずはその原因の分析から取り掛かりました。
その結果、Sさんは教わったその場では解き方を理解しているのですが、テスト時までには解き方を忘れてしまっていたり、どのパターンの問題をどの解き方で解くのかを混乱してしまっているということが判明したのです。こういうタイプの生徒は、往々にして問題の解き方をテキストの何ページの何番目に書いてあったからこの解き方だ、というふうに順番で解き方を覚えていて、それで理解したつもりになっていることが多いのです。
そこで私が行った対策は、カード式ランダム学習法と名付けた方法です。これは保護者の方に協力してもらい、塾のテキスト(本科教室・栄冠への道、ツールなど)から私が厳選した問題を縮小コピーして問題部分を切り取り、カード用紙に張り付けて問題カードを作成してもらい、これをランダムな順に解かせて、問題を見ただけで解き方が浮かんでくるようになるまで毎日繰り返し反復練習させる方法です。
カードの裏面には表面の問題の途中式や解答と共に問題を解く上で必要な考え方や重要な公式などをSさん本人に書き込ませ、書きながら覚えさせるとともにカードを裏返せば直ぐに答え合わせができるようにして学習の効率化を図りました。
この対策を続けていった結果、期待通りSさんの塾でのカリキュラムテストの成績は向上し、また点数も良い状態で安定してきました。
算数の本当の実力をつける方法
しかしこの時点ではまだSさんは出題範囲の決まっていない実力判定テストなどではなかなか点数が上がらず伸び悩んでいたのです。
その原因を探ったところ、解き方がパターン化されている問題は解けるようになっても、初めて見るパターンの問題は比較的簡単な問題でも依然として解けるようになっていないということが分かってきました。
そのために次に私が行った対策は、初めて見るパターンの問題に対する取り組み方を格段に改善するための訓練(問題分析再構築訓練法)を徹底的に行うことでした。
具体的には、銀本(みくに出版)の算数の一行問題から私が選んだ問題を解かせ、その際、問題で訊かれていることは何かや既に分かっていることは何か、決められている条件は何かといったことをきちんと把握すること、問題文中で大切な箇所や間違いやすい個所に線を引いたり印をつけること、図を描いて考えることなどを指導し、問題分析力を強化させる訓練を行い、また分析の結果どの公式や解き方を適用すると解けるかを見つける練習をさせました。
こうした訓練を繰り返していくうちに次第にSさんは初めて見るパターンの問題も解けるようになっていき、次第に算数に対する自信がついてきたのです。
そして
そうしているうちに9月になり、過去問演習を行う時期になりましたが、この時期も過去問と並行して銀本での訓練を引き続き行わせ、問題の解答力や得点力の強化に努めました。
というのは中大横浜の入試問題は難しい問題を解けることよりも、基礎から標準レベル位までの問題を広い分野にわたり早く正確に解けることが重要だからです。
また中大横浜の算数の入試答案では途中式も書かせる問題が多いので、過去問や銀本での演習の際は解答の書き方も徹底して訓練させました。
そして迎えた入試本番、Sさんは苦手だった算数で7割以上の得点を挙げることができ、見事に中大横浜中学に合格できました。これも私の対策を素直に実行してくれたSさんの努力やご家族のご協力のおかげと確信しております。
中央大学横浜中対策にオススメの教材
- 中学入学試験問題集 算数編(通称銀本)(みくに出版)
- 丸まる要点ノート理科(学研)
対策まとめ
お子さま一人ひとりに合った対策を、今から始めましょう
100人いれば100通りの受験。中学受験の対策は、お子さま一人ひとりで大きく変わります。
まずは現在の学習状況や目標を把握し、限られた時間の中でベストな方法をご提案いたします。
まずは無料相談で、お悩みをお聞かせください。今後の方向性を一緒に見つけましょう。
無料相談もこちらお問い合わせください

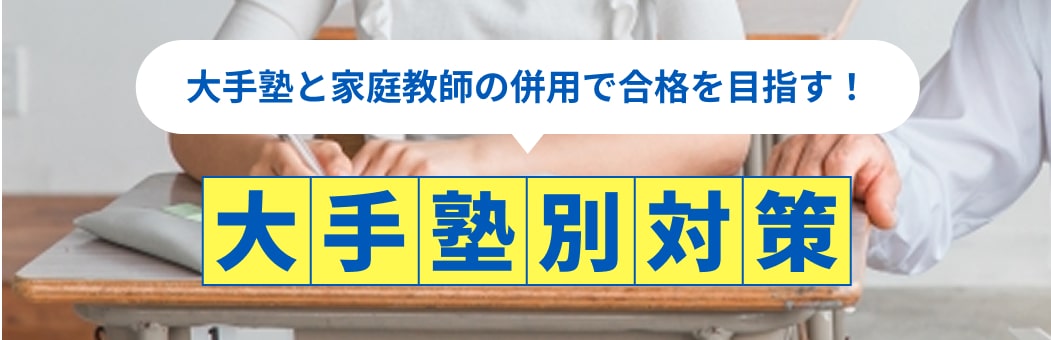
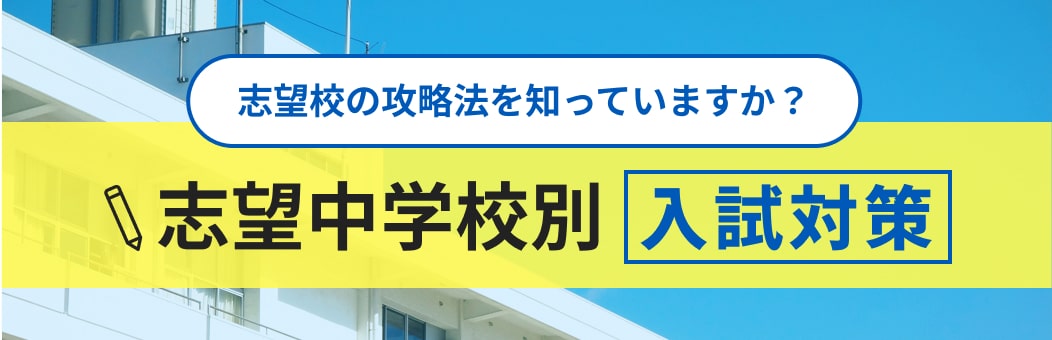
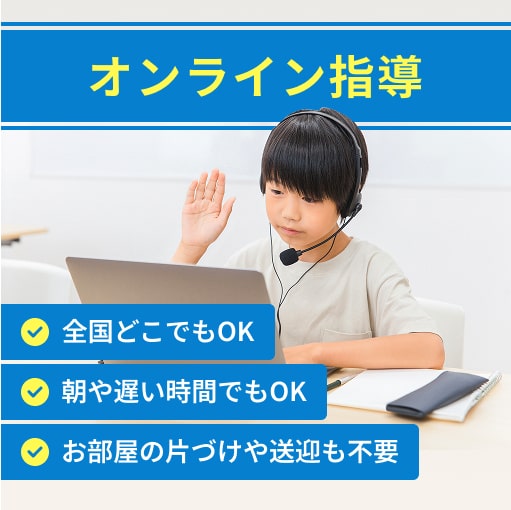
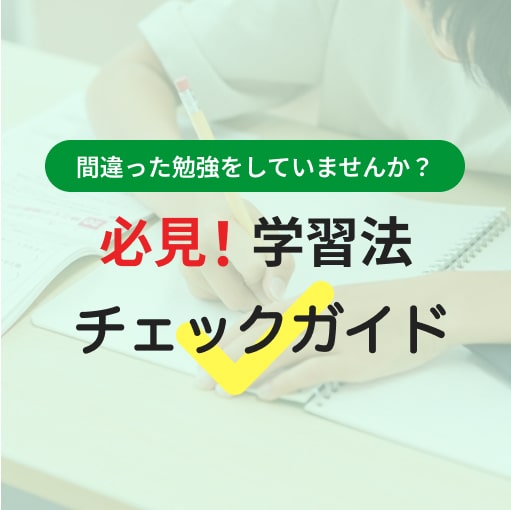
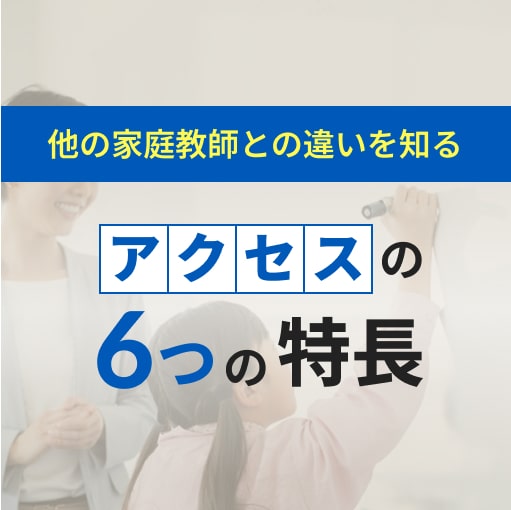
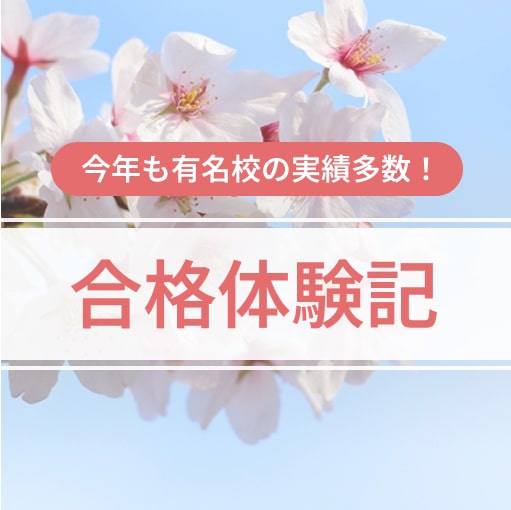
中央大学横浜中攻略のポイントは問題の性質を見抜ける力です。
解答時間のわりに問題数が比較的多いので、解けなければならない問題を素早く見分ける能力と、早く正確に問題を解く能力が要求される。
問題自体は基本的で難しくはないが、高得点が要求されるのでミスをしたり苦手分野を持ったりしないことが重要。
算数では途中式や考え方を書かせる問題が多いので普段からきちんと書くようにすることが肝心である。