
| 学校名 | 慶應義塾普通部 |
|---|---|
| 共学・別学 | 男子校 |
| 住所 | 〒223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町1丁目45−1 |
| ホームページ |
総合難易度:★★★★☆
- 算数難易度:★★★★☆
- 国語難易度:★★★★☆
- 理科難易度:★★★★★
- 社会難易度:★★★☆☆
慶應普通部について
慶應普通部は、慶應大学付属中学唯一の男子校です。
問題はそれ程難しくはありませんが、論理的な思考力や日常の出来事から真実を読み取る分析力・観察力、考えや筋道を端的に表現する表現力が要求される問題が比較的多く出題されますので、高得点を狙うには十分な練習が必要です。
また解答時間が少ないわりに問題数は多く、手際の良い処理が要求されます。
入試の特長
①理科がかなり特殊でレベルが高いので、理科が得意な生徒はかなり有利。
②学力検査だけでなく体育・面接がある。
③理科・社会の配点が高いのが特徴。
科目別の分析
科目別出題形式・タイプ分析
| 科目 | 配点 | 時間 | 問題数 | 難易度 | 記述・要途中式 | 難問出題率 | 出題タイプ | 合格最低ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 40分 | やや多い | やや難 | 10% | 15% | A | 65% |
| 算数 | 100点 | 40分 | 多い | 標準 | 100% | 15% | AB | 65% |
| 理科 | 100点 | 30分 | 多い | やや難 | 15% | 20% | AB | 60% |
| 社会 | 100点 | 30分 | やや多い | 標準 | 35% | 10% | A | 70% |
出題タイプの解説
- Aタイプ全体の9割以上が知識や公式を知っていて、その活用法が分かっていれば解ける出題の学校。
- Bタイプ全体の3割以上が正解を出すために、思考力や発想力を必要とする問題の学校。
- ABタイプ全体の1割から3割がBタイプ(正解を出すために思考力や発想力を必要とする問題)の学校。
科目別出題傾向
| 科目 | 出題されやすい単元・形式 |
|---|---|
| 国語 |
●物語、小説、伝記 ●随筆、紀行文、日記 ●漢字の書き取り(特に同音異義語、同訓異字) ●空欄補充、細部の読み取り、心情・情景の読み取り |
| 算数 |
●四則計算 ●数の性質、数列・規則性 ●平面図形、立体図形 ●論理・推理、集合 ●速さ・旅人算 ●場合の数 |
| 理科 |
●生物分野は難易度も高く多く出題される。(特に身近な動物・植物) ●てこ、滑車・輪軸 ●気象、光の性質、物質の状態変化 ●物体の運動 |
| 社会 |
●日本地理 ●日本の歴史 ●時事問題 ●公害・環境問題 |
慶應普通部の科目別攻略方法
国語の攻略方法
国語の出題傾向と学習方法
選択問題は紛らわしいものが多いので文章を正確に読み取る練習が必要。
配点的には少ないが記述問題も必ず出題されるのでポイントを押さえた表現ができるようにする。
知識問題は漢字の同音異義語・同訓異字を中心に練習。
試験で高得点をとるポイント
問題の難易度を素早く見抜き、解き易いものから手際よく解いてゆく。途中式は必ず書き、最後まで解ききれなくても図だけでも描いて残して、部分点を拾っていきたい。
算数の攻略方法
算数の出題傾向と学習方法
図形や場合の数、規則性、推理・論理、速さ・旅人算を中心に他の分野も時々出るので、他の分野も含めて早く正確に解ける練習が必要。途中式や計算を書かせるのできちんと途中式や計算を書き残しておく習慣をつける。
筋道を立てて考えたり規則を見つけ出す訓練が重要。
試験で高得点をとるポイント
問題の難易度を素早く見抜き、解き易いものから手際よく解いてゆく。計算ミスが無いように正確に処理する。
理科の攻略方法
理科の出題傾向と学習方法
身近な生物の特徴を図鑑などで覚えておく。 日常よく使われる道具や身近な現象を理科の内容と結び付けて考える訓練が重要。実験結果や図やグラフのデータから読み取り考察する練習も必要。
試験で高得点をとるポイント
問題数が多いので早く解ける問題からどんどん手際よく解いてゆく。計算問題はそれ程難しくないので確実に得点できるようにする。
社会の攻略方法
社会の出題傾向と学習方法
図やグラフ・写真から考えられること・読み取れることがわかるようにする。記述問題対策も充分行うこと。
分野の枠を超えた融合問題に慣れる。
時事問題への対策もおろそかにしない。
試験で高得点をとるポイント
選択問題から手際よく解いていき、配点の高い記述問題にも充分時間をかけられるようにする。
科目別類似問題傾向の学校
| 科目 | 問題傾向が似ている学校 |
|---|---|
| 国語 |
青山学院中等部、西武学園文理中学校 |
| 算数 |
武蔵中学校、麻布中学校、開成中学校、立教新座中学校 |
| 理科 |
城北中学校、灘中学校、東京電機大学中学、千葉日本大学第一中学校、聖光学院中学校 |
| 社会 |
開成中学校、桐光学園中学校、横浜中学校、日本大学第三中学校、東海大学附属相模 |
プロ講師による合格までの指導体験記
プロ講師による指導実例
私は、毎年のように慶應付属中学へ生徒を合格させてきていますが、私がどのようにして生徒を慶應普通部へ合格させているのか、その方法の一例をここでご紹介したいと思います。ここ近年の実例として、K君(仮名)の家庭教師として指導を行った時のお話をさせていただきます。慶應普通部を受験される予定の方のご参考になれば幸いです。
K君はSAPIXに通う生徒で、塾のクラスはD(真ん中よりやや下)に所属する新6年生(指導開始時)の活発な男の子でした。
K君やK君のご両親は、私がK君の指導を開始した時点で既に慶應普通部への進学を強く希望していましたが、その時点でのK君の成績は4科目総合偏差値が49(塾内の組分け・入室テスト)で、正直な話このままでは慶應普通部合格はかなり厳しい状況にありました。
それでも私は受験指導のプロである以上、結果を出すことが私の使命であると強く肝に銘じ、K君やご両親の想いに必ずや応えてあげなければと決意したものです。
プロ講師は生徒の弱点をどう分析するか?
私が最初に取り組んだことは、K君の現在の学習現状を詳しく調べ、問題点とその原因を探ることでした。
これを私は精密検査と呼んでいますが、K君のテストの結果や答案の書き方はもちろん、塾での授業の受け方、塾の他の生徒や先生との関係、普段の家庭での勉強時間や使用教材、学習内容、学習方法、生活のリズムや勉強の時間帯、自由時間の過ごし方、学校での友人関係、家族関係、メンタルな面に至るまで可能な限り詳細に現状を調べ、問題点を洗い出します。
その結果、K君の現在の一番の問題点は国語の読解問題でしばしば点数が取れていないこと、またその原因は次に挙げることが大きな要因であることをつきとめました。
それは、K君の語彙力がかなり小さいことや、K君は文章中に難しい語彙があるととたんに文章全体が難しいと思ってしまうために、難しい語彙が多く出てくるような文章では問題を解く以前に拒絶反応が出てしまい、こんな問題は僕には解けないと弱気になってしまうということでした。
文章に拒絶反応を示す生徒…そこで行った対策とは
そこで次に私が使った指導テクニックは、語彙活用力徹底強化法というものです。これは語彙の中でも特に感情や気持ちを表す心情語や、抽象的な概念をあらわす語句の意味や使い方を生徒に集中的に覚えさせて語彙力の強化を図るとともに、それ以外の語句で意味の解らないものが文章中に出てきた場合は前後関係や語句を構成している漢字などから生徒に意味を類推するようにさせるという訓練方法です。
具体的には、言葉力1200(学研)という教材を使い、そこに出てくる語句のうち私が厳選した語句を一つずつカードの表に書かせ、裏には語句の意味とその語句を使った例文を書かせて語句カードを作り、これをランダムな順番に並べて、表の語句を見てその意味が言え、更にその語句を使った例文が作れるようにするという訓練を繰り返し練習させるとともに、塾の教材を用いて、文章中に意味の解らない語句が出てきたときにその語句の意味を類推させたり、どの部分をヒントにすればその語句が類推できるのかということを徹底的に指導・訓練しました。
こうした訓練を繰り返していくうちに次第にK君は語彙力がついてきて、難しい語彙の多い文章題でも解けるようになっていき、国語に対する自信が出てきたのです。
プロ講師が教える理科対策
国語以外にも、K君は身近な出来事・現象を題材とした理科の問題も苦手としていましたが、よりによってこの類の問題は慶應普通部の入試で多く出題されるようなタイプの問題なのです。
塾の教材にも市販の教材の中にも身近な出来事に特化した問題集は無いようでしたので、私が行った指導テクニックは、中学入学試験問題集 理科編(みくに出版)から、身近な出来事や現象を題材にした問題をピックアップして、身近な出来事が理科のどの原理と結びつくのかや、どのように捉えていけば理科の問題として捉えることができるのかを考えさせた上で、問題を解かせる練習を数多く行わせるというものです。
その結果K君はそのタイプの問題への苦手意識が無くなり、点数を取るコツを掴みました。
また慶應普通部は身近な動植物に関する問題もよく出題されますが、入試問題ではカラーではなく白黒の図やシルエットで動植物が描かれているので、カラーの図鑑で学習していると色に頼って動植物を覚えてしまい、入試本番で戸惑ってしまう事もあり得ますので、自然図鑑(Do!図鑑シリーズ)(福音館書店)という白黒の本を使い身近な動植物やその観察方法を覚えさせるようにしました。
そして
9月以降は過去問を活用して慶應普通部の入試問題対策を徹底的に行いましたが、慶應普通部の入試では難しい問題を解くことよりも、標準レベル位までの問題を早く正確に解けることが要求されますので、過去問をただ解いて間違い直しをさせるだけでなく、過去問をどういう時間配分でどの問題から取り掛かるべきかや、解かなくてもよい問題(捨て問)はどれかを見極める訓練に活用し、限られた時間内で1点でも多く得点する技術を習得させました。
また慶應普通部の入試では少しのミスが命取りになることがあるので、ミスを防ぐための問題の読み方や線・印の付け方、答案のチェックの仕方も徹底して訓練させました。
こうして迎えた入試本番、K君は本人の予想で4科目合計で7割以上の得点を挙げることができ、無事慶應普通部に合格することができました。
慶應普通部対策にオススメの教材
- 中学入学試験問題集 理科編(通称銀本)(みくに出版)
- 言葉力1200(学研)
- 自然図鑑(Do!図鑑シリーズ)(福音館書店)
対策まとめ
お子さま一人ひとりに合った対策を、今から始めましょう
100人いれば100通りの受験。中学受験の対策は、お子さま一人ひとりで大きく変わります。
まずは現在の学習状況や目標を把握し、限られた時間の中でベストな方法をご提案いたします。
まずは無料相談で、お悩みをお聞かせください。今後の方向性を一緒に見つけましょう。
無料相談もこちらお問い合わせください

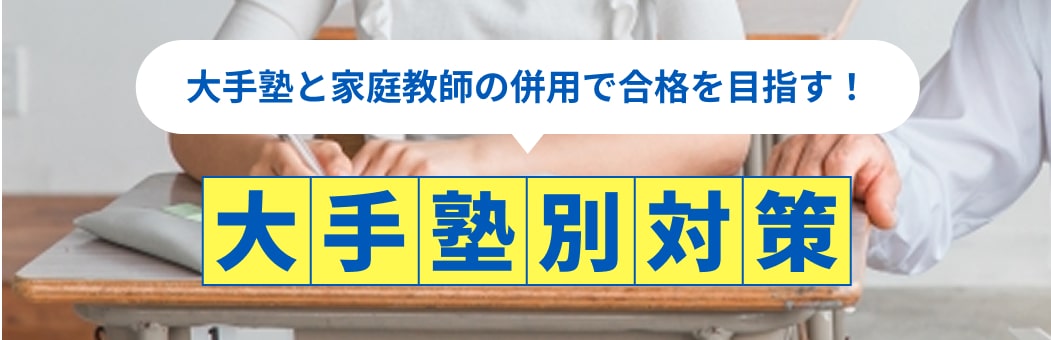
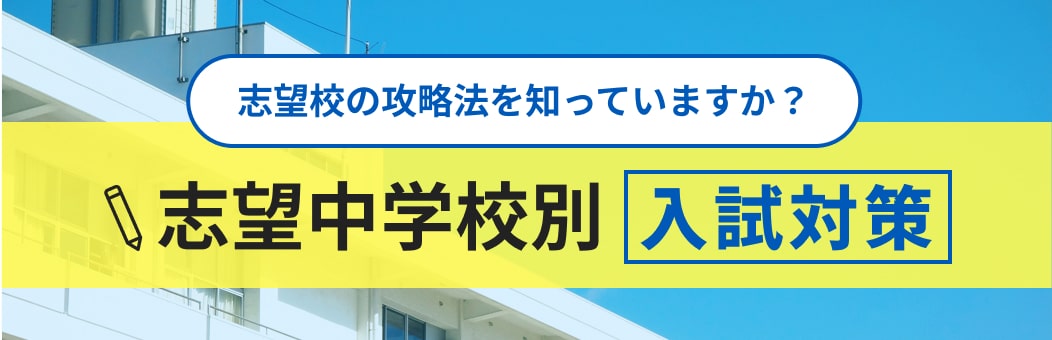
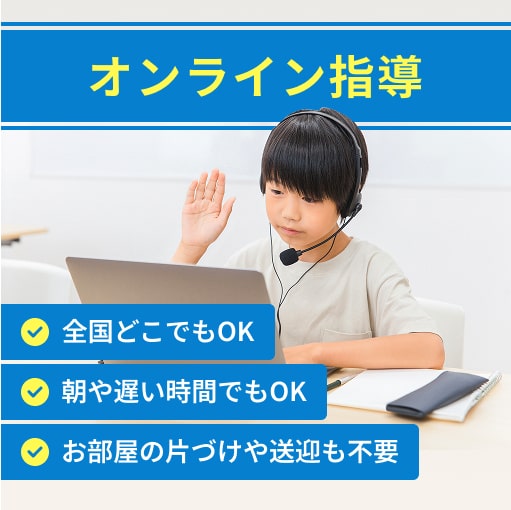
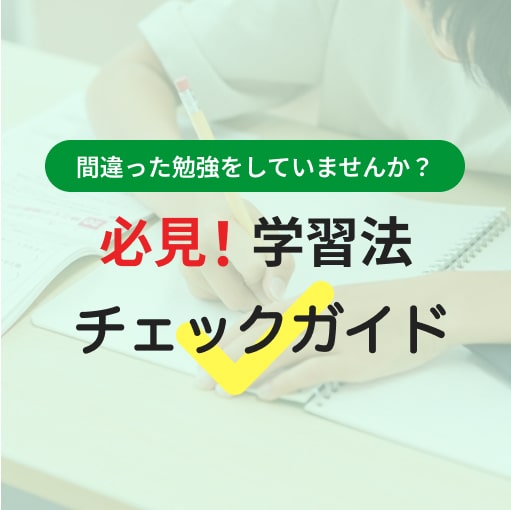
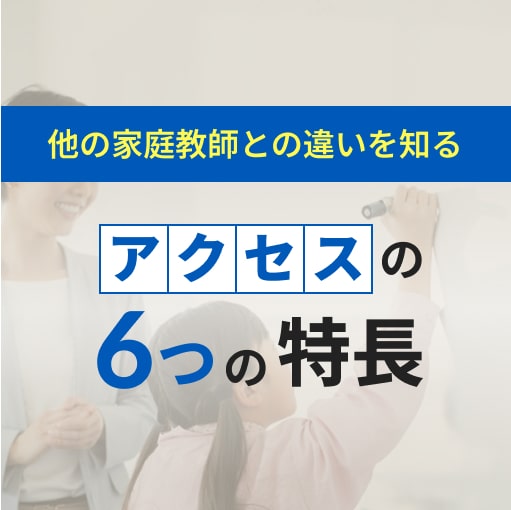
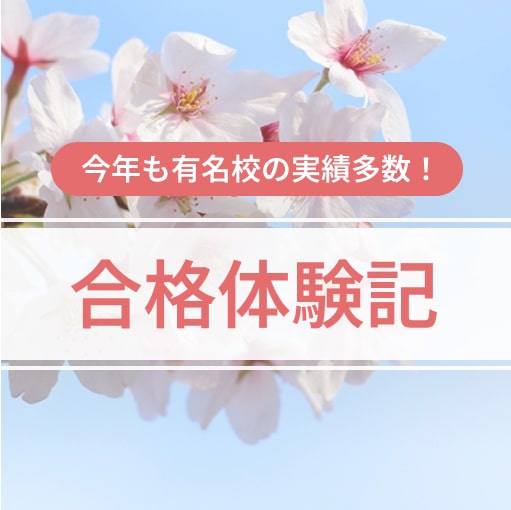
解答時間のわりに問題数が多いので、解けなければならない問題を素早く見分ける能力と、早く正確に問題を解く能力が要求される。
また筋道をたてて論理的に考え、表現する力や、ものごとを分析して考えていく力が必要になっていくので、普段から問題を解く際に、どのように考えたら問題が解けるのかを意識しながら論理的に考える訓練をしていく必要がある。